一級建築士の一次試験(学科)に令和7年度で合格しました。
実はその前年、資格学校に通っていたのですが…資格学校に通い始めた後に結婚式の次の日が試験日であることを知り、そんなハードスケジュールこなせないなと思い受験を断念。笑
「やってしまった」と落ち込みながらも、翌年は過去問反復で独学挑戦し、合格を掴みました。
この記事では、2024年1月から合格した2025年9月までの道のり、その所感をお伝えします。
今後受験される方の助けになれば良いなと思います。
一級建築士の講座を受講(2024年1月〜2024年7月)
最初は資格学校TAC(対面)に通いました。
理由は以下になります。
- 値段が他社に比べ圧倒的に安い
- 試験のコツとかを知りたかった
- 時間が取れないので効率的に勉強したかった
TACの良さについては下記のブログにて解説しています。
いいなと思ったら記事のアフィリのリンクから資料請求していただけるとかなり嬉しいです。笑
一級建築士試験の資格学校を比較!コスパで選ぶならTACがおすすめ【2025年最新版】
受講講座について
「一級 学科本科生」という1月開講の講座を受講しました。
特徴は下記になります。
- 構造、法規、施工、計画、環境設備について一通り勉強できる。
- 一番スタンダードなプラン
- 予習はいらない、復習がメイン 週一開講
次に自分の所感を話していきたいと思います。
※くだらないエピソードもありますがお付き合いください。笑
対面講座から通信講座へ変更
私は最初、TACの一級建築士講座を対面授業で受講していました。
講師の方が目の前で解説してくれる安心感はあったのですが、授業の進行スピードが速く、ついていくのが正直大変でした。
そこで途中から通信講座(オンライン受講)に切り替えました。
これが結果的に大正解。
分からなかった箇所を何度でも見返せるので、理解が深まりましたし、通学時間をまるごと勉強時間に変えられる点が非常に効率的でした。
自分のペースで学べるというのは、仕事と両立している社会人には本当にありがたいです。
講座は自分のペースでできる通信講座がおすすめ
授業内容の質とその後の独学への好影響
授業では、各科目を体系的に学べる構成になっており、特に「解法のコツ」や「出題傾向」を具体的に教えてもらえたのが印象的でした。
このおかげで、講座修了後の独学フェーズにもスムーズに移行できたと思います。
中でも法規の授業は特に助かりました。
最初は条文だらけで挫折しかけましたが、講師の方が「考え方の整理法」や「時間配分のコツ」を丁寧に教えてくれたので、理解が一気に進みました。
正直、法規以外はテキストあれば独学でいけそうだけど、法規だけは受けないとダメだなと思うほどでした(笑)。
解法のコツを体系的に学べる、法規は特におすすめ!
衝撃の日程被り(余談)
受験を決意して、勉強し続ける中ふと試験日っていつだっけと思い検索すると
「7月28日」
え、まって、結婚式の次の日やんってなりました。一週、二週前後なら許容範囲だったのですが、流石に次の日はだめだなと思いその年の受験は断念
ここで言いたいのはこんなズボラな私でも合格できたので、時間をとり、コツコツ勉強すればみなさん一級建築士の現状学科だけですが、受かりますよと伝えたいです。笑
翌年に独学で挑戦:(2025年1月〜2025年7月)
2025年1月から本格的に独学を開始。仕事では毎月45時間以上の残業がありましたが、スキマ時間を活用し、勉強し、なんとか合格することができました。勉強時間は下記になります。
- 平日:通勤+夜に1〜2時間
- 休日:丸一日で8時間
使った教材は2024年版のTACのテキスト+過去問のみ。新しい参考書を買い足すのではなく、同じ問題を繰り返し解く方針を徹底しました。
仕事との両立で勉強しなければならなかったのでより効率的にやることを徹底しました。
色々試行錯誤しながらたどり着いた私の勉強法について示していきたいと思います。
通勤時間の勉強について
電車通勤だったので、基本座れないことが多く、立ちながらできるスマホで勉強しました。
webで見れる「井澤式 建築士試験 実例暗記法」のブログ記事を参考に計画の事例を勉強したり
施工や計画など暗記しなければならない基準の数値を暗記カードアプリ(Word Holic)にまとめ通勤時間を有効活用しました。
それぞれのリンク下記になります。
「井澤式 建築士試験 実例暗記法」
http://kentikushi-blog.tac-school.co.jp/archives/cat_1300293.html
暗記カードアプリ(Word Holic)
https://www.langholic.com/wordholic
通勤時間はスマホで勉強できるものに限定
満員電車でもノンストレス
平日の勉強について
平日は仕事を終えて帰宅すると21〜22時くらいになることが多かったのでその後勉強しました。
疲れもあるので、あまり頭を使わない計画、環境設備、施工の暗記系の科目の過去問をやり続けました。その際に注意したのは間違えたものを暗記カードに追加して、実践と間違えたところの復習のサイクルを回しました。
正直毎日継続はできませんでしたので、週1,2回眠たい時は無理せず寝ていました。笑
平日は仕事の疲れもあるので頭を使わない暗記系の計画、環境設備、施工をやる
休日の勉強について
休日は平日にできていない法規、構造を徹底的にやりました。法規についてはかなり頭を使うので、休日にしかできませんでした。笑
勉強を始めて序盤は法規、構造で半々の時間配分でやっていましたが、法規は法令集から答えを見つけ出す訓練を積めば、安定的に問題が解けるようになるので、試験日が近くなるにつれ構造にシフトしていきました。ただ法規の勘を鈍らせないように毎週一年分くらいは解くようにしていました。
休日は法規、構造を徹底的にやる
法規に慣れてきたら構造に割く時間を増やす
試験結果とその所感
試験の得点は結構ギリギリ攻めてしまいました。まあ受かってしまえば何でもいいやと思っています。笑
計画、環境設備、法規、構造、施工の試験当日の所感についてまとめていきたいと思います。
| 科目 | 得点 | 合格最低点(合格基準点) |
|---|---|---|
| 計画 | 14/20 | 11/20 |
| 環境・設備 | 16/20 | 11/20 |
| 法規 | 25/30 | 16/30 |
| 構造 | 19/30 | 16/30 |
| 施工 | 18/25 | 13/25 |
| 合計 | 92点 | 88点 |
計画、環境・設備
まずは計画、最初に思ったのは
「え、見たことない設問多くね?」
最初少し焦りましたが、落ち着いて問題を読んでいくと、過去問と同じ選択肢があり、消去法で選択肢を絞り解答することができました。
環境・設備は得意な科目であったので、特に難なく解けました。
新規問題は最初から捨てるつもりだったので、過去問にあった問題を確実に解いていった感じです。
法規
R6年から告示から出題されることとなり、問題の出題傾向が変わることが予想されましたが、基本過去問ベースの問題が多かったです。やはり安定的に得点できたので徹底的に勉強をやっておくことをおすすめします。
ちなみに告示から出題された分(直通階段の寸法)は問題を解いている時は気づきませんでした。
今のところは新傾向の問題、告示を最悪落としても問題なく及第点は取れそうな感じです。
構造、施工
構造については計算問題が新規の問題にやられ、出鼻を挫かれた感がありました。
ちょっと焦ってしまったのもあり、得点落としてしまいました。また応用が効かず、根本的な理論について理解できていなかったのが露呈した感はあります。ここは反省点です。
施工は過去問で出ていた範囲は問題なく解くことができ、及第点は取れたかなと思います。
私が思う学科に受かるポイント
結局過去問をいかに解けるようにするかが重要であると思いました。
しかし過去問を表面的に理解するのではダメで、
問題に出ている選択肢についてすべて⚪︎×を判断でき、それがなぜ間違っているのかの理由まで理解するところまで行うことが大切です。過去問を消去法で解けるレベルではダメです。
新規問題については予想不可能なので、予想して山を張るのは限られた試験勉強の時間の中でやるのはコスパが悪いような気がします。それより過去問を確実に理解する方が大切だと思います。
合格のポイント:過去問の全ての選択肢について正誤を判断できるまで持っていく
まとめ:忙しくても効率的にやれば合格できる
仕事をしながら、その残業45時間以上でも効率的に勉強を行えば、合格できます。
大事なのは過去問を徹底的に回し切り。過去問の全ての選択肢について正誤を判断できるまで持っていくことです。
あと、私の通っていたTACは他の資格学校より格安で、勉強を効率化できるテキストがもらえます。独学で過去問やるだけでもいけるとは思いますが、効率的にやるならあって損はないと思います。
資料請求はタダなので、気になる方はとりあえず資料請求からやってみてください。
体験講座もやっているはずです。
その時は下記のアフィリエイトリンクから資料請求していただけるととても嬉しいです。笑
↓
ではでは



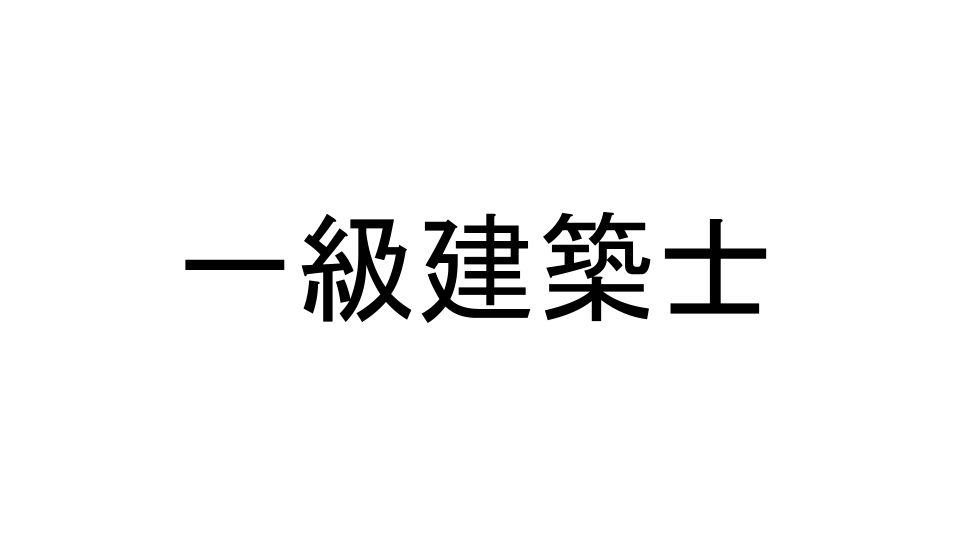
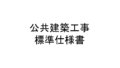

コメント