建築設備の施工を行うとき、必ず出てくるのが「防火区画の貫通部」の扱いです。
「ここって何センチ必要?」「防火ダンパーは必ず要るの?」など、現場で疑問が多いポイントですよね。
この記事では、とっかかりとして防火区画と建築設備に関する法令や仕様書の関係性を整理して解説します。
特にダクト・配管を例にして、施行令 → 告示 → 大臣認定・標準仕様書のつながりを理解していきましょう。
施行令が大枠を決める
まず基盤となるのは建築基準法施行令です。
第112条では「防火区画を貫通する設備には、火の通り道を遮断する措置を講じなければならない」と大枠が定められています。
つまり施行令は「やるべきこと」を抽象的に示している段階です。
具体的に「どういう性能で、どのように遮断するのか?」は示されていません。
告示が性能基準を示す
そこで登場するのが国土交通省告示です。
告示は、施行令の要求を具体化し、性能基準等を定めます。
例えば、
建設省告示第1369号
「特定防火設備(防火ダンパー)の構造方法を定める件」
建設省告示第1378号
「耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、
配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件」
といった形で、定められており、「具体的にこの基準を満たしなさいよ」という物差しを示すのが告示の役割です。
大臣認定と標準仕様書の二つのルート
告示の「物差し」に基づいて、現場で使える形に落とし込むのが次のステップです。ここで二つのルートがあります。
(1)大臣認定
メーカーが告示で定められた試験に合格した製品や工法について、国交大臣が正式に認める制度です。
例:
- フィブロック
現場では「この製品、大臣認定取れてる?」と確認するのが常です。
(2)公共建築工事標準仕様書
公共工事で使われる一般的な施工仕様をまとめたものです。国土交通省が作成しており、「標仕」、「国交省仕様」とも呼ばれます。
こちらも告示を基盤にして作られており、「大臣認定品を使わずとも、この仕様なら性能を満たす」という位置づけです。
例:
- ダクトの板厚規定等
- 防火区画を貫通する配管のモルタル充填等のルール
4. 整理するとこうなる
法令・仕様の流れをシンプルにまとめるとこうなります。
- 施行令:防火区画の貫通部には延焼防止措置が必要(抽象的な要求)
- 告示:性能基準を提示(性能の物差し)
- 大臣認定:告示の基準に基づき製品・工法を承認(個別解)
- 標準仕様書:公共工事での標準的な施工仕様を提示(一般解)
つまり、
告示が基盤となり、そこから「大臣認定」と「標準仕様書」という二つの道が広がる構造になっています。
5. まとめ
ダクトや配管の防火規定は、一見バラバラのルールがあるように見えます。
しかし整理すると、施行令 → 告示 → 大臣認定・標準仕様書という明確な流れになっています。
- 施行令=大枠のルール
- 告示=性能の物差し
- 大臣認定=製品ごとの承認
- 標準仕様書=公共工事での一般解
この法令、仕様書間のつながりを整理できていると根拠を提示しなさいとか言われた時に役に立つかもしれません。少しマニアックかもですが、、、
👉 次回は、具体的に「ダクトの板厚規定」や「防火ダンパー設置義務」などの個別規定を掘り下げていきます。




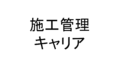
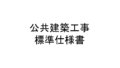
コメント